
お盆は、年に一度、ご先祖様や亡くなった大切な人たちの霊があの世から帰ってくるとされる、日本人にとって大切な行事です。一般的には8月13日から16日の期間に行われ、故人の霊をお迎えし、冥福を祈り、供養します。現代では職場がお休みになったり、帰省や旅行などに出かける人が増えたり、どちらかというと「夏休み」として楽しみにしている日本人も多いもの。実際、楽しいことや嬉しいことが一度にたくさん起こった時に「盆と正月が一緒に来たみたい」などと表現する日本語もあるほどです。
この記事では、お盆の由来や意味、2025年の盆休み期間、そして日本古来のお盆の過ごし方について、わかりやすく解説します。
※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。
お盆とは?意味と由来をわかりやすく解説
お盆の由来と歴史

お盆は、先祖や故人の霊を供養する行事です。8月13日から16日に行うのが一般的で、お盆の時期には、亡くなった人の霊が浄土、つまり死後の世界からこの世に帰ってくると考えられています。故人が生前を過ごした自宅に霊をお迎えして、冥福を祈るとともに霊魂を供養します。
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、仏教の「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」というお経に由来しているといわれています。
盂蘭盆経の「盂蘭盆(うらぼん)」は、サンスクリット語の「ウラバンナ」という言葉が起源だそう。これは、お釈迦さまの弟子が亡き母をお盆の時期に供養したことで母親は極楽往生を遂げたという故事がもとになっているようです。
死後の世界にいる故人を供養して弔うという仏教の風習が日本に伝わり、それが先祖を祀る行事となって、お盆の風習が民衆に定着していったと考えられています。
今日では、普段は遠く離れて暮らす家族も、お盆には実家に帰省し、先祖の霊を供養するというのが習慣となっています。
お盆の目的
繰り返しになりますが、お盆の目的は祖先の霊を供養し冥福をお祈りすることです。
一般的なお盆の期間の8月13日から16日までは、企業も休業となることがほとんど。小中学校や高校、大学は夏休みの期間中で学校の授業はありませんし、部活動なども休みとなることが多いです。土日と連続する暦の年は大型連休となるので、遠方からでも帰省して家族や親せきで一緒に過ごす人も多いでしょう。
お盆とは、死後の世界から戻って来る霊を自宅でお迎えし、家族や親せき一同でにぎやかに過ごしながら、故人を弔うという行事なのです。
2025年のお盆はいつからいつまで?【お盆休み・期間まとめ】
2025年(令和7年)のお盆は、8月13日(水)~8月16日(土)の4日間。11日(月)は「山の日」で祝日ですが、12日は火曜日で平日なので、多くの人は13日から17日(日)までの5連休となりそうです。
9日(土)から11日(月)は3連休なので、もし12日(火)を休むことができれば、9日(土)から17日(日)までの9連休とすることも可能です。大型連休となるので、帰省するだけでなく、旅行に出かける人も多いかもしれませんね。
東京のお盆はなぜ7月?地域で違うお盆の時期
旧暦・新暦の違い

ここまで、お盆は8月の13日から16日までの期間が一般的だとお伝えしましたが、実はこれは古い暦での考え方なんです。明治時代に導入された「新暦」では、7月13日から16日までの期間がお盆とされています。
新しい暦では7月がお盆とされているのに、旧暦の8月のお盆が人々に定着しているのは不思議ですよね。
東京のお盆:7月13日~16日
一部の地域では、新暦の7月をお盆の期間だと考えられている地域もあります。その一つが東京です。新盆は都市部を中心に執り行われているようです。
地方との違い(8月が主流)
一方で、都市部から遠い田舎の地域では、旧盆の8月が定着していることが多いとされています。これは、かつては多くの日本人が農業に携わっており、新暦の7月15日ごろは農業が忙しい時期であることが関係しているとされています。生業である農業が忙しい時期に、連休をとって落ち着いて故人を悼むのは難しいもの。新しい暦に変わったとしても、田舎の農村地域では新盆が広まらなかったという見方もあるようです。
一方で、農村地域ではない東京では新暦が定着したといわれています。
また、地域の産業に合わせるなど、各地によって、さまざまなお盆の時期があるようです。
お盆に何をする?行事・風習・食べ物
迎え火・送り火

お盆の初日に霊を迎えるために焚く火を「迎え火」と言い、見送る時に焚く火を「送り火」といいます。
迎え火は玄関前やお墓などで行うもので、焙烙(ほうろく)と呼ばれる素焼きの平らなお皿の上で、オガラ(皮を剥いだ麻の茎)に火を灯して焚きます。お墓で迎え火をした場合は、盆提灯に火を移して自宅に持ち帰ります。自宅に着いたら別の盆提灯に火を移し、玄関先で黙とうをしてから火を消します。
これは、迎え火によって故人を自宅にお迎えすると考えられているためです。自宅に迎えたらもう迷子になることがないため、迎え火は消しても大丈夫ということになります。
送り火は迎え火の反対で、家の中で火を灯し、お墓もしくは玄関先まで故人を案内します。そしてお送りする場所で黙とうをしたのちに、火を消します。
お墓参りや帰省、家族との時間
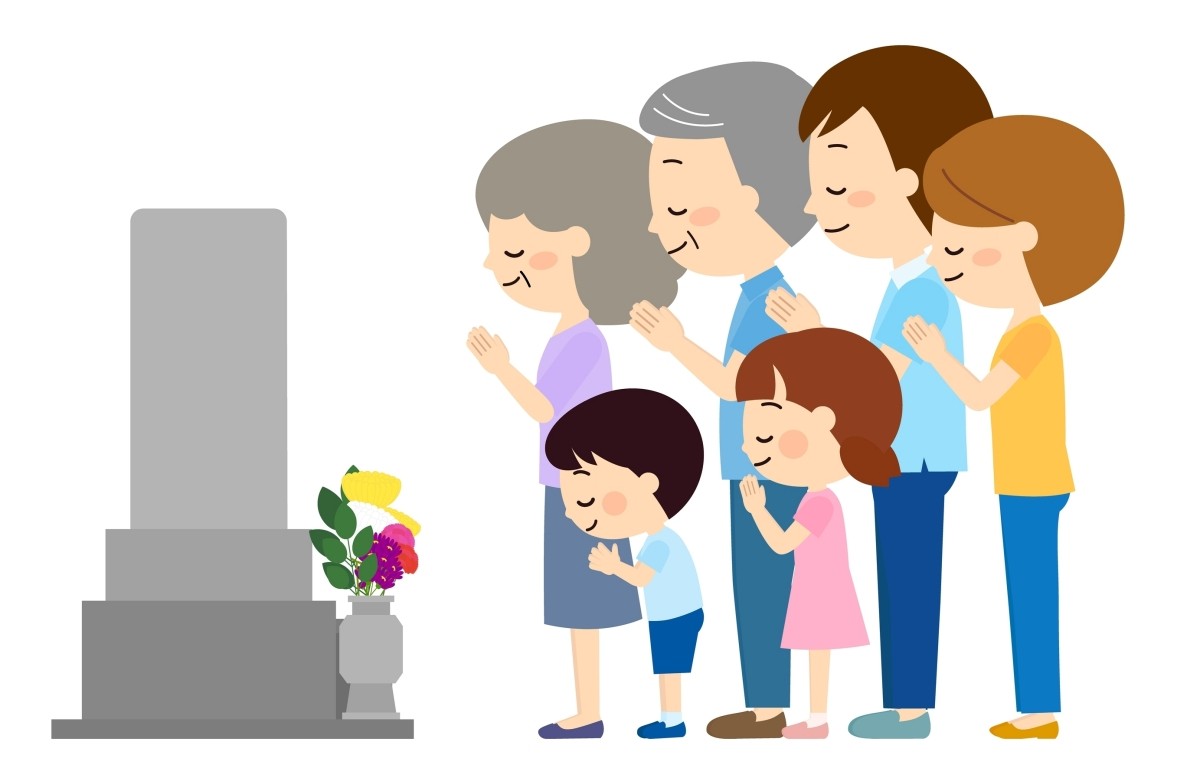
お盆の墓参りは、8月13日に行くのが一般的といわれています。というのも、13日は迎え盆と呼ばれ、ご先祖様をお迎えに行く日。そのため13日にお墓参りをし、先祖の霊を迎えるための「迎え火」を焚くというのが一般的な手順のようです。ただし、必ず13日に行かなければいけないという決まりはないようです。
お盆の供物・精霊馬と精霊牛

お盆のお供え物は「五供(ごく)」と呼ばれる5種類のものを供えるのが基本とされています。五供とは、お香やお花、ロウソク、お水、食べ物の5つ。それぞれ線香やお花、ろうそく、お菓子などを供えます。
また、きゅうりで作る馬を模した「精霊馬(しょうりょううま)」と、なすで作る牛を模した「精霊牛(しょうりょううぎゅう)」もお盆のお供え物として一般的です。精霊馬と精霊牛は、割り箸や竹串をきゅうりやなすに刺し、足に見立てて作ります。お盆のときに特別に作られる棚「精霊棚(しょうりょうだな)」に飾るのが良いとされています。
このきゅうりとなすは、先祖の霊が自宅とあの世を行き来する際に使う乗り物という意味合いがあります。自宅に戻って来るときは足の速い馬を、帰りは牛に乗ってゆっくりと帰ってほしい、という思いが込められているそうですよ。
ちなみに、なぜきゅうりとなすなのかというと、どちらも夏野菜でお盆の時期に手に入りやすいからだそう。
また、お盆は先祖の霊が帰って来るので、故人が生前好きだった食べ物でもてなすのが良いともいわれています。故人の好物を供えるのも素敵な供養になりそうですね。
海外にもお盆はある?

ここまで日本のお盆についてご紹介してきましたが、海外にもお盆のような風習はあります。
中国の「中元節」は旧暦の7月15日に行われ、紙のお金や贈り物を焚き上げることで先祖に贈り、供養するという風習です。
アメリカの「ハロウィン」も、死者の霊を迎える夜とされています。ただ、最近では主に子ども達が仮装をしてお菓子を貰いにいく行事として定着していますね。日本でも仮装を楽しむイベントとして人気があります。
メキシコの「ディア・デ・ロス・ムエルトス」は「死者の日」と呼ばれ、11月1日から2日間行われます。故人を迎えるための供え物を作ったり、カラフルな仮装やスカルメイクをしたりします。
死者を迎える行事や祭りは、様々な文化や宗教にもとづいていろいろな形で行われているんですね。
2025年のお盆の過ごし方
2025年のお盆の帰省ラッシュは、出発のピークが8月10日(日)、田舎から現住所の都市圏へ戻る「Uターンラッシュ」は8月15日(金)から16日(土)にかけてと予想されます。お盆の期間は交通機関が混雑しますが、特に10日と15日はかなり混雑しそうですね。飛行機や新幹線を利用するなら、早めに席を予約したほうがいいでしょう。
最後に、お盆の時期に日本を訪れるなら、チェックしておきたいお盆の行事をご紹介します。
大文字送り火

8月16日に京都市で行われる送り火の行事。京都市街を取り巻く各々の山に「大」「妙」「法」文字や船や鳥居の形のかがり火を灯します。お盆にこの世を訪れた霊たちがこの送り火を見ながら浄土に帰っていくといわれています。
👉京都 五山送り火鑑賞 バスツアー(Sunrise Tours JTB)
盆踊り

「盆踊り」は、お盆の期間中の夜に、地域の寺の境内などで行われる踊りのこと。浄土から帰ってきた先祖の霊を迎えておもてなしするという意味合いのほかに、地域の人々が交流するという意味合いもあります。音楽や踊りは地域によってさまざま。古くから親しまれた「音頭」や「民謡」だけでなく、最近は「流行りのポップス曲」や「アニメソング」に合わせて踊ることもしばしば。
また、盆踊りは基本的に誰でも参加OKな場合がほとんど。地域によっては踊り手が決められていることもありますが、ほとんどの場合は飛び入り参加OKです。外国人観光客にも人気の旅行のアクティビティとなっているようです。
お盆は日本人にとって夏の大切な行事
古来、先祖の霊を供養するための行事だったお盆は、現代の日本では楽しみな夏休み期間として捉えられています。
道路や公共交通機関、観光地や宿が混雑したり、お店や施設、公的機関がお休みになったりする場合もあるので、事前に情報を確認するようにしましょう。
ぜひ、楽しい夏休みを過ごしてくださいね!
参考文献:
田中宣一・宮田登 編『三省堂年中行事事典 改訂版』初版,三省堂,2012,全458ページ
新谷尚紀 監修『和のしきたり 日本の暦と年中行事』初版,日本文芸社,2007,全238ページ
三浦康子 監修『季節を感じて日々を楽しむ くらし歳時記』初版,成美堂出版,2024,全191ページ







Comments