【2025年最新】日本で大地震発生!?どうすればいい?地震情報確認アプリやサイトも要チェック!

日本は「地震大国」として知られており、ごく小さな揺れを含めれば、ほぼ毎日どこかで地震が発生しています。特に地震に不慣れな外国人旅行者にとっては、この事実に不安を感じる方もいるでしょう。地震の研究や予測は日々進歩していますが、その発生を正確に予知することは、現在のところ不可能です。
「南海トラフ巨大地震」や「首都直下地震」といった大規模な地震の可能性についても、耳にされたことがあるかもしれません。また、「7月5日に日本で大地震が起きる」というような根拠のない噂も話題になっています。この記事では、日本の地震に関する背景や、地震発生時の対策・準備、そして身を守るための具体的な行動まで、皆様に安心して日本での滞在を楽しんでいただくための情報をご紹介します。
日本の地震、どれくらい知っている?気になる疑問を解説!
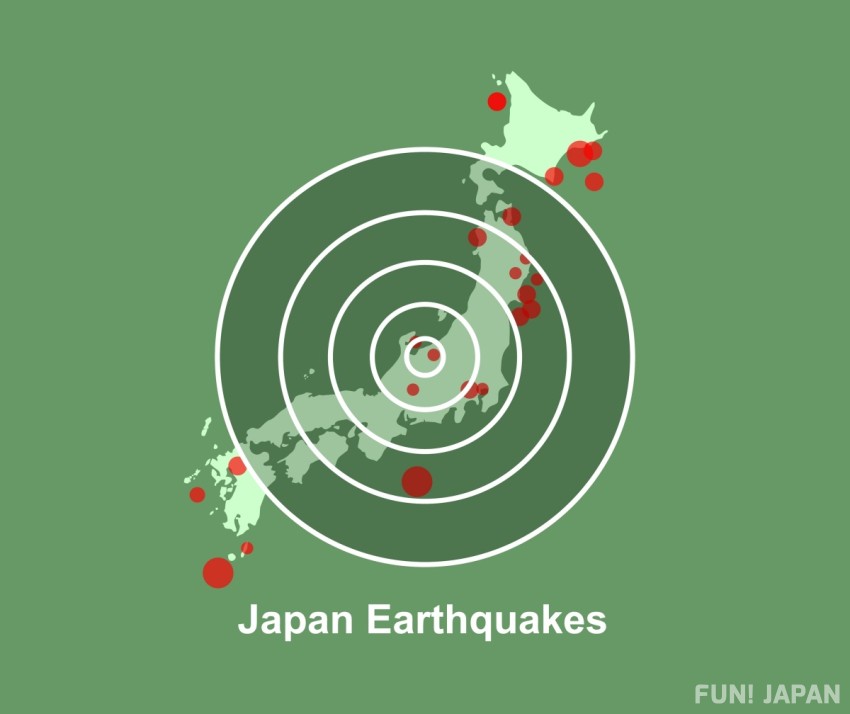
日本は世界でも有数の地震大国ですが、「地震が多い場所や少ない場所ってどこ?」「震度とマグニチュードは何が違うの?」といった疑問を感じたことはありませんか?
ここからは、そんな日本の地震に関するよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q1)日本の活断層ってなに?地震帯とは違う?
「活断層」とはずれ動き、将来も活動すると考えられる断層のこと。活断層が急にずれ動くことが地震を引き起こす原因です。⽇本の周辺には約2,000もの活断層があり、未発見のものも多数存在します。そのため、全国どこでも地震が発⽣する可能性があると言われるのです。
Q2)震度とマグニチュードの違いは?
「震度」は、ある場所での地震による揺れの「強さ」(揺れの大きさ)に対して、「マグニチュード(M)」は地震そのものの「大きさ」(地震の規模、エネルギー)をあらわします。
Q3)日本で地震はどれぐらいの頻度で起きている?
日本では、人が体感できる規模(震度1以上)の地震は、平均年間で約2400回発生し、震度5以上の地震も10回程度起きています。日本では地震が頻度に起きていて、「いつでもどこでも地震が起きる可能性がある」と言えるでしょう
※気象庁「震度データベース」による、過去5年間の平均地震回数
Q4)日本で地震が多い場所は?
気象庁「震度データベース」による、過去5年間の都道府県ごとの平均地震回数を比較すると、地震が特に多い地域として以下のエリアが挙げられます。
- 東北地方の太平洋沿岸(福島県、宮城県、岩手県、青森県)
- 関東地方(茨城県、東京都、千葉県、栃木県)
- 中部地方(長野県、岐阜県、特に石川県)
- 九州南部(特に鹿児島県)
Q5)日本で地震が少ない場所は?
上記と同じデータで比較すると、地震の少ない地域として以下のエリアが挙げられます。
- 九州北部(佐賀県、福岡県)
- 中国・四国地方(鳥取県、香川県、山口県、岡山県、島根県)
- 関西地方(滋賀県、奈良県、三重県)
ただし、「少ない=安全」というわけではありません。過去にあまり地震が起きていない地域でも、大地震が発生する可能性はあります。
※気象庁「震度データベース」による、過去5年間の都道府県ごとの平均地震回数の比較
日本の地震震度階級

日本における地震の震度階級は、気象庁が定める震度0から震度7までの10段階で、地震による揺れの程度を客観的に示すものです。特に震度5弱以上は、防災対応の必要性が高まるため、迅速な情報伝達がなされます。これらの震度階級は、揺れが人に与える影響、屋内外の状況、構造物の被害状況などを目安として、住民が適切な防災行動をとるための重要な指標。各震度階級の概要をご紹介します。
- 震度0:人は揺れを感じないが、震度計には記録されるごく微弱な地震。日常生活には全く影響がないレベル。
- 震度1:屋内で静かにしている人の中には、わずかな揺れを感じる程度の地震。吊り下げられたものがわずかに揺れることがある。
- 震度2:屋内で静かにしている人の大半が揺れを感じる程度の地震。電灯などの吊り下げられたものがはっきりと揺れる。
- 震度3:屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる地震。食器が音を立てるなど、家屋が軽く揺れるのがわかる。
- 震度4:ほとんどの人が驚く揺れ。電灯などの吊り下げられたものが大きく揺れ、座りの悪い置物が倒れることがある。
- 震度5弱:大半の人が恐怖を覚える揺れ。棚の食器や本が落ちることがあり、固定していない家具が移動することがある。
- 震度5強:行動に支障をきたす揺れ。棚の食器や本が落ちるものが多くなり、テレビが台から落ちることがある。家具が転倒する場合もある。
- 震度6弱:立っていることが困難になる揺れ。固定していない家具のほとんどが倒れ、壁のタイルや窓ガラスが破損・落下することがある。
- 震度6強:はいずらないと動けないほどの揺れ。多くの建物で壁のひび割れや損壊が見られ、耐震性の低い木造建物では倒壊するものもある。
- 震度7:耐震性の高い建物でも大きな被害を受ける揺れ。多くの建物で倒壊あるいは著しい損傷が生じ、山崩れや崖崩れが発生することがある。
地震の「予知」と「予測」の違いは?さらに「予言」もある?

地震に関する情報でよく使われる「予知」、「予測」という言葉。これらには明確な違いがあります。
- 地震予測:地震の発生時間、場所、大きさ(マグニチュード)の一部またはすべてを地震発生前に推定すること。しかし、現在の科学技術では正確に知ることができません。
- 地震予知:予測の中でも特に確度が高く、警報につながるもの。
- 地震予言:科学的根拠に基づかない情報のこと。例えば、日本の漫画家・霊媒師のたつき諒氏の作品から「2025年7月5日に日本で大災害が発生する」という「予言」が広まり、これにより香港人からの旅行キャンセルも報じられています。
つまり、現在のところ、地震の発生を「予知」することはできませんが、過去のデータから「予測」は行われています。また、「予言」は根拠のない情報なので、公的機関からの正確な情報を手に入れましょう。
「緊急地震速報」の「予報」、「速報」、「警報」とは?その違いは?

スマホやテレビから鳴る「緊急地震速報」は地震の揺れが来る前や来る時に知らせてくれる非常に重要なシステム。そのなかで使われる「予報」「速報」「警報」という言葉について解説します。
- 予報:地震直後に発表される初期情報で、震源や規模の速報値。まだ精度は低い場合がある。
- 速報:揺れが来る数秒〜数十秒前に、テレビやスマホへ一斉に届く情報。身を守るための迅速な行動を促す。
- 警報:予想震度が原則震度4以上の地域に限定して発表される、特に重要な情報。警報が鳴ったらすぐに身を守る行動を促す。
つまり、地震が起きてすぐに発表されるのが「予報」や「速報」で、その中でも特に揺れが大きいと予想される地域に限定して出されるのが「警報」と考えると分かりやすいでしょう。この警報が鳴ったら、すぐに身の安全を確保する行動を取ってください。
地震に伴い発生する災害や被害

地震の揺れそのものだけでなく、それに伴って様々な二次災害が発生する可能性があります。これらの災害についても理解しておくことで、より安全に行動できるでしょう。
地震による主な被害には、以下のようなものがあります。
- 津波:海底の地震で発生し、沿岸部に押し寄せる巨大な波。
- 建物倒壊:強い揺れにより建物が壊れること。
- 火災:ガス漏れや電線ショートなどが原因で発生。
- 土砂災害:揺れで崖崩れや地すべりが起きること。
- 液状化現象:地盤が液体のように軟らかくなり、建物が傾く現象。
特に大都市で地震が起きると、以下のような被害も考えられます。
- 家具などの落下物:家具が倒れたり、窓ガラスや外壁が落下したりする危険がある。
- 電話や通信の混乱:電話回線が混み合い、インターネットにもつながりにくくなる可能性。
- 移動困難:道路が寸断されたり、電車が停止したりして、人々の移動が非常に難しくなる。
- 電気、ガス、水道の停止:停電、水道の断水、ガスの停止が起こる可能性。
日本旅行中に地震への不安があるなら、これらの災害に備え、事前に自分で簡単な防災グッズを準備してみてくださいね。
関連記事
地震が来たらどうする?地震が起きたらどこに逃げる?

地震はいつ、どこで起きるか分かりません。日本滞在中に地震に遭遇した際、冷静に対応できるよう、地震が来る前、来た時、来た後の行動について確認しておきましょう。
地震が来る前のすべきこと

旅行中にできる「事前準備」は限られますが、以下の点に注意すると良いでしょう。
- 旅行保険の確認: 万が一の事態に備え、旅行保険への加入を検討しましょう。特に、地震による損害や緊急医療費用、航空便の遅延・キャンセルなどが補償されるプランを選ぶと安心です。
- 避難経路のチェック: 緊急時に迅速に避難するために、滞在するホテルの部屋に貼ってある避難経路図や非常口、階段、屋外の集合場所などを確認しておきましょう。
- 身の回りの安全の確保: 大きな家具が倒れてこないか、ガラスや照明の真下にいないかなど、簡単な安全確認をします。就寝時には、倒れそうなものから離れた場所に寝るといいでしょう。
- 連絡手段の確認: 家族や友人と連絡が取れるように、Wi-Fi環境やローミング設定、国際電話の使い方を確認すると安心です。また、緊急通報番号(警察:110番、消防・救急:119番)警などの緊急番号も覚えておくと役に立ちます。
- 地震情報を把握できるツールの準備: スマートフォンに地震速報アプリを入れたり、地震情報が確認できるサイトをブックマークするものいいでしょう。地震の揺れが来る前にアラートが鳴ることもあります。
- 日本語の簡単な防災用語を覚える: 「地震(じしん)」「津波(つなみ)」「避難(ひなん)」「高台(たかだい)」など、緊急時に役立つ日本語をいくつか覚えておくと、周囲の指示が理解しやすくなります。
- 非常用グッズの準備: 旅行中に全てを用意するのは難しいですが、非常食や水、モバイルバッテリー、懐中電灯など、最小限の非常用品を持っておくと安心です。
地震が来た時にすべきこと

実際に地震が起きた際には、身の安全を守ることを最優先に行動しましょう。
- まずは身を守る: テーブルの下など、落下物から身を守れる場所に素早く移動し、頭を腕やバッグなどで保護します。頭上に落ちてくるものがない場所が安全です。
- あわてて外に出ない: 建物の外はガラスや看板などが落ちてくる危険があるため、揺れが収まるまでは無理に外へ出ないようにします。
- 火の元に注意: キッチンなどにいた場合は、無理に火を止めようとせず、まずは自分の身の安全を確保。揺れが収まった後に火を消します。
- エレベーターは使用しない: 揺れを感じた際やその直後は、エレベーターを使いません。万が一閉じ込められた場合は非常ボタンで救助を呼びましょう。
- 周囲の状況を冷静に確認: ガラスの破片や倒れた家具など、ケガの原因になりそうなものに注意しながら、避難が必要な場合は落ち着いて行動してください。
地震が来た後のすべきこと

揺れが収まった後も、余震や火災などの危険があるため、引き続き注意が必要です。
- 安全な場所へ避難する準備: 建物の倒壊や火災の危険がある場合は、周囲の状況を確認しながら、近くの避難所や広い場所(公園や学校など)に避難しましょう。
- 避難情報を確認する: スマートフォンやホテルのフロント、近くのスタッフなどから最新の避難情報を確認。外国人観光客向けの多言語対応アプリ(Safety tips など)も活用するといいでしょう。
- 落ち着いて行動する: 周囲が混乱している場合でも、あわてず、冷静に。避難時には手荷物を最小限にし、周囲と協力して行動してください。
- 避難所でのルールを守る: 避難所に行った際には、案内に従って指定された場所にとどまり、秩序を保つことが重要です。
- 正確な情報を得るようにする: SNSなどの不確かな情報に惑わされず、政府や自治体の公式情報を確認するように心がけましょう。
「今地震がありましたか?」地震情報をリアルタイムで確認するには?

旅行中に揺れを感じた時や、ニュースで地震を聞いた時、「今の揺れは地震だったのか?」と確認したい時は、スマホアプリや公式サイトを活用すれば、正確な情報をリアルタイムで得られます。
「通知が届く」地震の位置や情報を手早く確認できるスマホ「アプリ」
- Safety tips:外国人旅行者向けに開発された防災アプリ。緊急情報を多言語で通知。
- Yahoo!防災速報:地震、津波、豪雨などの速報を地域別に通知。英語表示にも対応。
- My Earthquake Alerts & Feeds:世界の地震速報や防災情報を提供する英語対応アプリ。
地震情報の詳細を確認できる「サイト」、「ニュースサイト」
- 気象庁 地震情報(www.jma.go.jp):日本の公的機関による公式の震源地・震度情報を掲載。
- NHK NEWS WEB(https://www.nhk.or.jp/):地震速報や注意情報をリアルタイムで配信するニュースサイト。
- ウェザーニュース(weathernews.jp):地震マップのほか、SNS投稿を集約されて現地の状況を確認できる情報サイト。
地震を体験できる施設5選

日本の地震対策の知識を深めるだけでなく、実際に揺れを体験できる施設があります。
- そなエリア東京(東京臨海広域防災公園):https://www.tokyorinkai-koen.jp/sonaarea/
- 池袋防災館(東京消防庁):https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/taiken/ikebukuro/index.html
- 立川防災館(東京消防庁):https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/taiken/tachikawa/index.html
- 本所防災館(東京消防庁):https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/taiken/honjo/index.html
- 東京都北区防災センター(地震の科学館):https://www.city.kita.lg.jp/safety/disaster/1002639/1002675.html
日本へ出発する前はこの記事を参考に準備をすると不安を和らげることができます。ぜひ参考にしてください。
